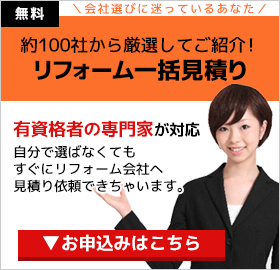リフォームで地獄を見た人、続出!2025年版 建て替えを選ぶべき3つのサイン
現在の住まいの状況、不満や不安をもとに家族で検討を重ね、リフォームで計画を進めると決めたとき、リフォームの規模は、一般的には全面リフォーム・リノベーション、あるいは大規模なリフォームになります。しかし、本当にリフォームが最適解なのでしょうか?2025年現在、中古住宅市場の活性化や金利上昇、建築資材の高騰など、住まいを取り巻く環境は大きく変化しており、建て替えとリフォームのどちらを選ぶべきか、慎重な検討が必要です。
その場合、まず何から検討を始めたらいいのでしょうか?全面リフォーム・リノベーション、あるいは大規模なリフォームを計画するとき、小規模なリフォームと違い、事前にしっかり検討すべきことがあります。全面リフォーム・リノベーション、あるいは大規模なリフォームの場合、新築への建て替えと同じように、ライフプランの整理と資金計画からしっかり検討を重ねる必要があるのです。
次の2点が、全面リフォーム・リノベーション、あるいは大規模なリフォームを成功させるコツです。
- ・ライフプランを整理する
- ・リフォームの目的を明確にする
ライフプランと住まいの将来設計
建て替えを選んでも、リフォーム・リノベーションを選んでも、計画を具体的に進めていくにあたり、まず必要なことは、ご自身のライフプランを整理して、明確にしておくことです。
これから、リフォーム・リノベーションを計画する住まいが終の棲家になるのか。年齢的な条件を考えたとき、終の棲家として長くても20年程度の住処になるのか、30年以上にわたって住み続けることができそうか。将来のライフプランに不安があり、10年~20年程度で売却する可能性があるのか、もしくはリフォームして賃貸に出すのか。現在の住まいをきちんと相続してくれる人がいるのかなど。これらの考え方や状況によっても、リフォームの計画・規模は大きく変わります。
ライフプランの整理にあたり、計画を思い立った段階で、現在の住まいを建て替えた場合、リフォームした場合、もしくは売却して他の不動産を購入、いわゆる住み替えといった場合に、これから新居で迎える生活で、いつ、どのくらいのお金がかかり、あわせて新しい住まいには何年くらい住むのか、といった、あらゆるシミュレーションを行ない、将来のキャッシュフローを想定しておくことが大切です。2025年現在では、不動産価格のAI予測サービスなども活用することで、より精度の高いシミュレーションを行うことが可能です。
特に、高齢者になれば、主な収入は年金だけとなります。たとえ、建て替えるにせよ、リフォームするにせよ、5年周期で発生する住まいの維持メンテナンス費用を将来の支出計画に組み込んだうえで、収入とのバランスも検討しなければいけません。つまり、建て替えにせよ、全面リフォーム・リノベーションにせよ、老後の生活資金が不足することがないようにしておくことが必要です。2025年現在では、リバースモーゲージなど、老後の資金を確保するための金融商品も多様化しています。
また、一戸建の場合、介護状態になってしまうといった万が一の状況に備え、階段の上り下りをせずワンフロアで生活できるような間取りの工夫をはじめ、将来のバリアフリーに備えた対策といったプランのチェックも重要となります。2025年現在では、介護ロボットの導入や、見守りサービスの利用なども視野に入れ、より安心して生活できる住まいづくりを検討しましょう。
リフォームの目的を明確化する
すべてが新しくなる新築建て替え工事と比較して、リフォーム・リノベーションの場合、何のためにリフォーム・リノベーションを行なうのかという目的をはっきりさせることが大切です。2025年現在では、省エネ性能の向上や、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化など、地球環境に配慮したリフォームも重要な選択肢となっています。
そのためには、現在お住まいの建物状況を、できるかぎり正確に把握することが必要です。
昭和56年(1981年)6月1日に建築基準法が改正され、昭和56年(1981年)6月1日以前に建築確認申請を提出したものは【旧耐震基準】の建物、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認申請を提出したものを【新耐震基準】の建物と言って、建物の構造基準が大きく異なっています。2025年現在では、住宅性能表示制度を活用することで、建物の耐震性能や省エネ性能などを客観的に評価することができます。
一応の目安として、新耐震基準のものであれば、構造補強工事にかかるリスクとコストが小さくなり、旧耐震基準のものだと、構造補強工事リスクとコストが大きくなります。もちろん、耐震基準では判断できず、現在のお住まいの基礎のクラックはどの程度か、床下と屋根裏はどんな状況になっているか、外壁のシミ、外部建具、内部建具の閉まり方の状況などを直接確認。必要に応じて機械を使った精密耐震診断なども実施したうえで、総合的に判断する必要があります。
その結果を踏まえて、構造補強工事が必要なのか、住宅性能を維持させるためのメンテナンスリフォームに留めるのか、間取りや最新の住宅設備をはじめ、現在では当たり前のリフォームメニューとなっている省エネ性能を高める大規模リフォームを決断するのか。あわせてお客様のライフプランと資金計画を照らし合せながら、必要な資金とリフォーム・リノベーションにかけられる資金をそれぞれ検討して計画的に行なうことが大切なのです。
特に戸建ての場合、屋根塗装工事や外壁塗装工事など、外回りに足場を組まなければいけない工事は、工事時期を決めて一度に済ませたほうが、効率的かつ長期的にみて低コストなリフォーム工事ができます。
建て替え vs リフォーム:コストとメリット・デメリットの比較
リフォームと建て替え、どちらを選ぶべきか悩む方は多いでしょう。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
建て替えのメリット
- ・最新の耐震基準や省エネ基準を満たすことができる。
- ・間取りやデザインを自由に設計できる。
- ・設備の老朽化を気にせず、快適な生活を送ることができる。
- ・住宅ローン減税など、税制上の優遇措置を受けられる。
建て替えのデメリット
- ・費用が高額になる。
- ・工事期間が長くなる。
- ・仮住まいが必要になる。
- ・固定資産税が上昇する可能性がある。
リフォームと建て替え、どちらを選ぶべきか悩む方は多いでしょう。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
リフォームに関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

 リノベーション HOME
リノベーション HOME