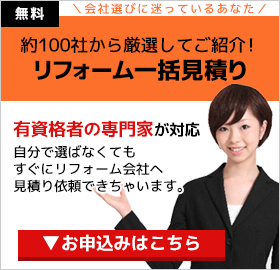税理士が教える!住宅取得等資金贈与をした場合
その年の1月1日で20歳以上の子や孫に住宅の取得や自宅のリフォーム資金を贈与した場合には、次のような特例があります。住宅取得を支援するための贈与税の特例制度は、制度内容や要件が頻繁に見直されます。そのため、最新情報を確認し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
- 一定金額の非課税
- 相続時精算課税制度の特例
この記事では、これらの特例制度の概要と、2025年における注意点について解説します。ただし、税務に関する内容は専門性が高いため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
1. 適用要件
この特例の適用を受けるためには、様々な要件がありますが、そのうち主なものは次の通りです。2025年現在における要件は、税制改正により変更されている可能性がありますのでご注意ください。
1.1 適用対象者
その年の1月1日で20歳以上の子、孫、ひ孫など(直系卑属)に対する贈与であること (※年齢要件は要確認)
贈与を受ける子や孫の合計所得金額が2,000万円以下であること (※所得要件・金額は要確認)
1.2 資金や住宅の使途
贈与を受けた金額全額を、住宅の取得・リフォームに充てること
贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに住むか、あるいは、贈与を受けた年の翌年12月31日までに確実に住む見込みであること
1.3 中古住宅の要件
次のいずれかに該当すること (※築年数要件は要確認)
耐火建築物の場合→築25年以内であること
耐火建築物以外の場合 → 築20年以内であること
一定の耐震構造基準に適合するものであること (※耐震基準は要確認)
1.4 リフォームの要件
工事費用が100万円以上であること (※金額は要確認)
工事費用全体の1/2以上が居住用部分に関するものであること
床面積の1/2以上が居住用であること
床面積が50m2以上240m2以下であること
次のいずれかを満たしていること
区分所有の場合は区分所有の床または壁の全部についての修繕または模様替えであること
居室、調理室、浴室、便所その他の部屋の床または壁の全部について行う修繕または模様替えであること
耐震基準に適合させるための家屋の修繕または模様替えであること
2. 住宅取得資金贈与の非課税制度
2.1 制度の内容
贈与した金額のうち、以下の金額が非課税となります。非課税限度額は、税制改正により変更されている可能性がありますので、必ず確認してください。
| 贈与年 | 一般の贈与 | 省エネ・耐震性の高い住宅 |
|---|---|---|
| 平成25年中 (過去の情報) | 700万円 | 1,200万円 |
| 平成26年中 (過去の情報) | 500万円 | 1,000万円 |
※1 省エネ・耐震性の高い住宅とは次のものをいいます。
・省エネルギー対策等級4以上の住宅
・耐震等級2以上の住宅
1※2 東日本大震災の被災者については、平成25年・26年ともに次の通りとなります。
・一般の贈与→1,000万円
・省エネ、耐震性の高い住宅→1,500万円
3. 相続時精算課税制度の特例
3.1 制度の内容
ポイント1
通常の相続時精算課税制度と、住宅取得等資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例については、贈与者(あげた方)の年齢制限について、以下の違いがあります。
- 通常の場合→65歳以上(H27.01.01以降の贈与については60歳以上)に対して
- 住宅取得等資金の贈与の場合
- 贈与者の年齢制限なし
- ・住宅の登記事項証明書
- ・請負契約書・売買契約書などの写し
ポイント2
また、相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までは贈与税がかからない(贈与者が亡くなった際に相続税が課税されます。)とともに、上記3の非課税と一緒に適用することができます。
[平成25年度](過去の情報)
・ 一般の贈与→700万円+2,500万円=3,200万円
・ 省エネ、耐震→1,200万円+2,500万円=3,700万円
[平成26年度](過去の情報)
・一般の贈与→500万円+2,500万円=3,000万円
・ 省エネ、耐震 → 1,000万円+2,500万円=3,500万円
3.2 手続き方法
与をした年の翌年2月1日~3月15日の期間内に、次の書類を添付して、贈与税の期限内申告書を提出することが必要です。
・相続時精算課税選択届出書
・受贈者(もらう方)の戸籍謄本、抄本などで、氏名・生年月日・贈与者(あげる方)の推定相続人であることを証明する書類
・受贈者の戸籍の附表の写しなどで、20歳達した日以後の住所または居所を証明する書類
・贈与者の住民票の写しなどで、氏名・生年月日・住所または居所を証明する書類
なお、2,500万円の特別控除で、贈与税額が0円になる場合でも、この手続きは必要となります。
税務署への申請は、e-Taxを利用することでオンラインで完結できるようになります。4. まとめ:専門家への相談で賢く節税
親子で住宅を購入する際には、贈与税や相続税など、様々な税金が関わってきます。税務に関する内容は複雑で、専門的な知識が必要となるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。税制優遇措置を賢く活用し、理想の住まいを無理なく手に入れましょう。
リフォームに関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください
(注) 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務に関する個別の判断やアドバイスを提供するものではありません。必ず税理士などの専門家にご相談ください。

 リノベーション HOME
リノベーション HOME