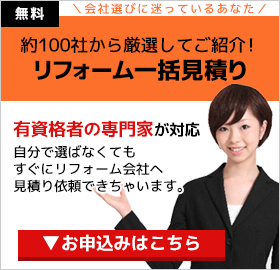税理士が教える!持ち分に注意 ~資金贈与をした場合
近年、親子が協力して住宅を購入するケースが増えています。住宅価格の高騰や、親世代からの資金援助など、様々な背景が考えられますが、資金の出し方によっては贈与税が発生してしまうことも。2025年現在、家族信託など、新たな資産承継の形も注目されており、住宅購入と合わせた検討が重要になっています。
この記事では、親子で住宅を購入する際の贈与税対策と、賢い資金計画について解説します。ただし、税務に関する内容は専門性が高いため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
1. 資金の拠出 ≒ 家の持ち分 は贈与の基本
例えば親子でお金を出し合って、中古住宅を購入される際、資金の拠出割合と家の持ち分について…
- (資金の拠出) (家の持ち分)
- 親 3,000万円⇒親 50%
- 子 2,000万円⇒子 50%
などとしてしまうと、親から子に500万円の贈与があったものとされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。
したがって、お金を出し合ってご購入される場合は、必ず資金の拠出=家の持ち分となるようにして下さい。2025年現在、共有名義にする場合は、各々の負担割合を明確にし、契約書などに明記することが重要です。
2. 既に資金の拠出と持ち分が違う場合の対策
万が一、資金の拠出割合と持ち分が異なってしまっている場合は、以下の対策を検討しましょう。ただし、いずれの方法も税務上の影響があるため、必ず税理士に相談してください。
◆対策1:錯誤登記をする
当初の50%ずつの登記が間違えていたものとして、正しく60%・40%の持ち分に登記し直す。
◆対策2:資金を返却する
登記した持ち分に合わせて、子が親に500万円返却する。
◆対策3:差額を貸借関係とする
金銭消費貸借契約書を作成し、その契約書に従って実際に返済する。2025年現在、親子間であっても、金銭消費貸借契約書を作成し、利息をつけて返済することで、贈与とみなされるリスクを軽減できます。
◆対策4:差額を贈与とし、贈与税の節税対策をする
・住宅取得等資金を贈与した場合の贈与税の非課税制度を適用する。(注)
・住宅取得等資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例を適用する。(注)
(注)上記「6.住宅取得資金の贈与をした場合」参照。
3. 住宅取得資金贈与の特例(2025年版)
親から子へ住宅取得資金を贈与した場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度があります。この制度は、住宅取得を支援するための重要な制度ですが、非課税限度額や適用要件は毎年変更されるため、必ず最新情報を確認してください。
2025年現在、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用するための主な要件は以下の通りです。(※必ず税理士にご確認ください)
- ・贈与を受ける人が、贈与者の直系卑属であること
- ・贈与を受ける人の所得が、〇〇〇万円以下であること (※金額は要確認)
- ・贈与を受ける人が、日本国内に住所を有していること
- ・贈与を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- ・取得する住宅が、一定の要件を満たす住宅であること
これらの要件を満たすことで、住宅取得資金として贈与された金額のうち、一定額までは贈与税が非課税となります。非課税限度額は、住宅の種類や取得時期によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。2025年現在では、省エネ性能や耐震性能に優れた住宅を取得した場合、非課税限度額が上乗せされるケースもあります。
4. 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与した場合に、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。この制度を活用することで、住宅取得資金を贈与する場合の税負担を軽減することができます。ただし、この制度を選択した場合、贈与者が亡くなった際に、贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する必要があるため、注意が必要です。5. 家族信託という選択肢
2025年現在では家族信託を活用することで、親の資産を管理・運用しながら、子供の住居取得を支援することが可能です。家族信託は、財産の管理・運用・承継を家族に託す制度で、遺言書の代わりとしても活用できます。家族信託を活用することで、贈与税や相続税対策を行いながら、柔軟な資産承継を実現できます。
6. 専門家への相談
親子で住宅を購入する際には、贈与税や相続税など、様々な税金が関わってきます。税務に関する内容は複雑で、専門的な知識が必要となるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。2025年現在では、オンラインで相談できる税理士も増えており、手軽に専門家のアドバイスを受けることができます。
リフォームに関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください
(注) 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務に関する個別の判断やアドバイスを提供するものではありません。必ず税理士などの専門家にご相談ください。

 リノベーション HOME
リノベーション HOME